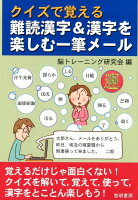先日、「豚」という漢字について書きました。「豚」という漢字の部首は「月(にくづき)」ではなくて「豕(いのこ)」だよ、という記事です。
「豚」という漢字の部首は「月(にくづき)」ではない - コバろぐ
この記事の冒頭のぼくと娘の会話を思い出していただきたい。
「お父さん、豚っていう字は身体に何も関係ないのになんで月ヘンなの?」
「それは月ヘンやない。“にくづき”っちゅーんや。しかし、それが身体をあらわすことは知っとんねんな。偉いやんけ!」
今回は、この豚の記事のときにスルーした「つきへん」と「にくづき」について書いていきます。

「つきへん」と「にくづき」
たとえば、「期」という漢字の右側と「臓」という漢字の左側には、同じ「月」という字がありますね。この場合、「期」の部首は「つきへん」で、「臓」の部首は「にくづき」になります。誠にめんどくさいですけど。
というわけで、まずは「つきへん」と「にくづき」、それぞれについて。
つきへん
「つきへん」の元になった漢字は、当然ながら「月」です。この字は、三日月が元になって出来た漢字です。
なので、意味的には暦に関係する字や、天体的事象をあらわす漢字が多いです。
「期」や「朧」などがつきへんの漢字ですね。
にくづき
「にくづき」の元になった漢字は「肉」です。
肉が月になる?って思われるかも知れませんが、肉という字、左右にはらってる部分が2つ重なってるじゃないですか、これが簡略化されて横棒になっちゃったカンジです。
というわけで、肉体に関係がある字には「にくづき」が使われています。
「臓」「肝」「胸」などですね。
「つきへん」と「にくづき」
元々、「つきへん」は横棒の右側が縦の線にくっついてなくて、ちょっと間があいていました。一方、「にくづき」は今と同じかたちでそこはくっついていました。
「つきへん」と「にくづき」は似てるけど違うものだったのです。
しかし、1949年に内閣より発表された「当用漢字字体表」から、「つきへん」と「にくづき」は同じ形になりました。ここからずっと今まで、「つきへん」と「にくづき」は同じカタチです。
まぎらわしいことに、今では辞書によってはどっちも「つき」でまとめられてたりもするので、誠にややこしい。
こうなると、「つきへん」と「にくづき」を仕分けするならば、その漢字の意味で見分けるしかありません。誠にめんどくさいですね。
オマケ:「ふなづき」
もうひとつ、似てるのに「廟」とか「兪」などの漢字につかわれている、月の横棒がナナメになってるやつがあるじゃないですか。
これは「ふなづき」といいます。「舟」という字が元になってるんですね。
「朝」とか「服」とかの部首は元々は「ふなづき」で月の横棒はナナメだったようですよ。
え?舟関係あんの?って思っちゃいますけど、月や肉とは違うんだということは覚えておいて損はないでしょう。得もないけど。
最後に
一見同じに見える字でも、意味や成り立ちは違うものだ、ということです。
漢字もただ覚えるだけだと味気なくて苦痛だったりしますけども、こういったことを考えるとススッと頭に入ってきたりするので、たまにはその漢字の成り立ちや意味を考えるのも悪くないですよ。
「しめすへん」と「ころもへん」を色分けしてみた。これでもう間違えない! - コバろぐ